
「うちの子、全然勉強しないんです…」
これは多くの中学生の保護者の方が抱える悩みです。
ですが、子どもは本来「できるようになりたい」「認められたい」という気持ちを持っています。その“火種”をどうやって大きくしていくか——そこに、保護者の関わり方が大きく関わってきます。
この記事では、子どもが自主的に勉強するようになるために、保護者としてどのように関われば良いのかを5つの視点から詳しく解説します。
「勉強しなさい」ではなく「関心を持つ」

「早く勉強しなさい!」という言葉は、つい口から出てしまいますよね。でもそれが毎日のように続くと、子どもは「勉強=怒られるからやるもの」と感じるようになります。
そこで大切なのは、“指示”ではなく“関心”を向けることです。
例えば、
- 「今日の理科、どんなこと習ったの?」
- 「お、ノート見せて。けっこう書いてるね!」
- 「ここの図、見やすくまとめてるじゃん」
といった声かけに変えてみてください。
「自分のやっていることを見てくれてる」と感じると、子どもはもっとやろうという気持ちになりやすいのです。
勉強を習慣にするには“リズム”が大事
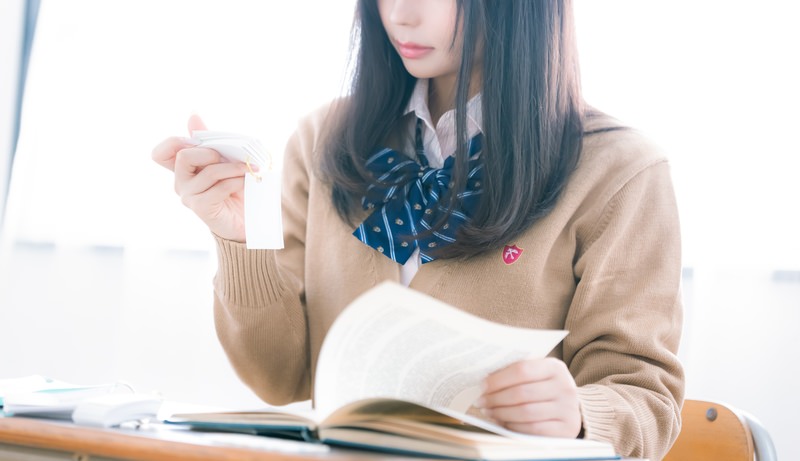
勉強を自主的にやる子の多くは、「毎日のリズムの中に勉強がある」ことが共通しています。つまり、やる気に頼るのではなく、習慣にしてしまうことがコツなのです。
習慣化のポイント
- 時間を固定する:例)夕食前の30分、入浴後の15分など
- 学習内容を決めておく:例)月曜は英単語、火曜は数学の計算
- やることリストを使う:終わったら消せる“見える化”がモチベーションに
「〇時になったら自然と机に向かう」というリズムができれば、それはもう“自主学習”と言えるでしょう。
小さな目標で「やればできる」を積み上げる
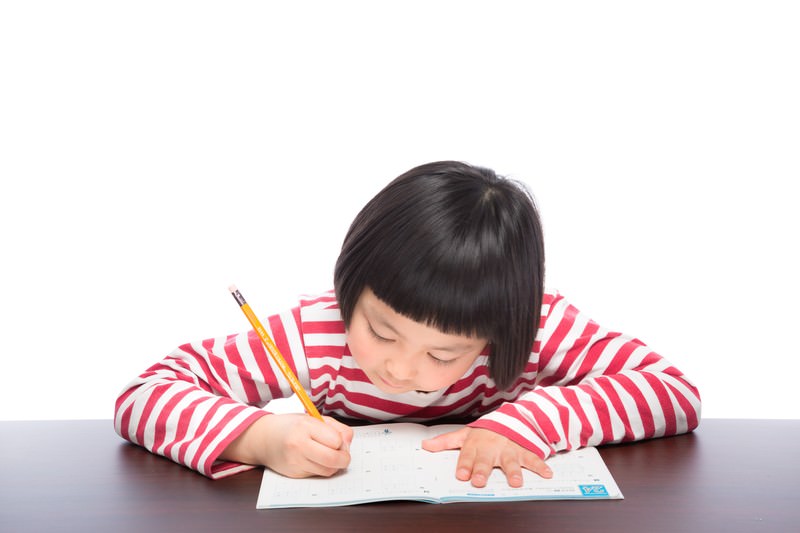
多くの子どもが勉強を嫌がる理由の一つは、「何からやればいいかわからない」「頑張っても無理だと思っている」ことです。
そこで大切なのは、小さな目標を一緒に立てることです。
- 「英単語、今日は5つだけ覚えてみよう」
- 「計算問題、3問だけ解いてみよう」
- 「教科書のこの1段落だけ読んでみよう」
そして達成したら、しっかり認めてあげること。
- 「お、やったね!ちゃんと続けててすごいじゃん」
- 「このペースならテスト前も安心だね」
小さな成功体験の積み重ねが、「自分はやればできる」という自己効力感を育て、自主性へとつながっていきます。
失敗しても責めない。むしろチャンス!

勉強がうまくいかない時、点数が悪かった時、どう声をかけていますか?
「だから言ったでしょ」「なんでちゃんとやらないの」
こういった言葉は、子どもの心を閉ざします。
大切なのは、失敗も成長の一部だと受け止める姿勢です。
- 「悔しいって思えるのは、本気で取り組んだからだね」
- 「どうして間違えたのか、一緒に見てみようか」
一度失敗を責められると、子どもは“バレないように隠す”ようになります。逆に、失敗しても支えてもらえるとわかれば、チャレンジを恐れず取り組むようになります。
自主性を伸ばす“環境”を整える

やる気だけで続けられる子はほとんどいません。自主学習の習慣をつくるには、環境の力を借りることもとても有効です。
環境づくりの具体例
- 学習スペースを整える(整理された机、照明、本棚)
- スマホ・ゲームは物理的に離す(時間制限や別室保管)
- 「親も一緒にやる」時間を作る(読書タイム・資格勉強など)
また、友達同士で励まし合える学習塾や、見守ってくれる大人がいる環境も、やる気を刺激するポイントになります。
信じて任せる力が、自主性を育てる

子どもが自分から動き出すには、時間がかかることもあります。ですが、その時に一番の支えになるのは「親が信じて見守ってくれている」という安心感です。
焦らず、怒らず、見守りながら声をかけ、支えていくことが、自主的な学習習慣を育てる一番の近道です。
保護者ができる5つのこと
- 「勉強しなさい」より「どんなこと習った?」
- 習慣化のために時間と内容を固定する
- 小さな目標と成功体験を積み重ねる
- 失敗を責めず、次へのステップに変える
- 環境を整えて、やる気を後押しする
この記事が、お子さんの「やる気のスイッチ」を押すヒントになれば幸いです。
「うちの子の場合はどうすれば…?」というご相談があれば、ぜひお気軽にお問い合わせくださいね。
勉強のモチベーションに関することは以下の記事も参考にしてください。

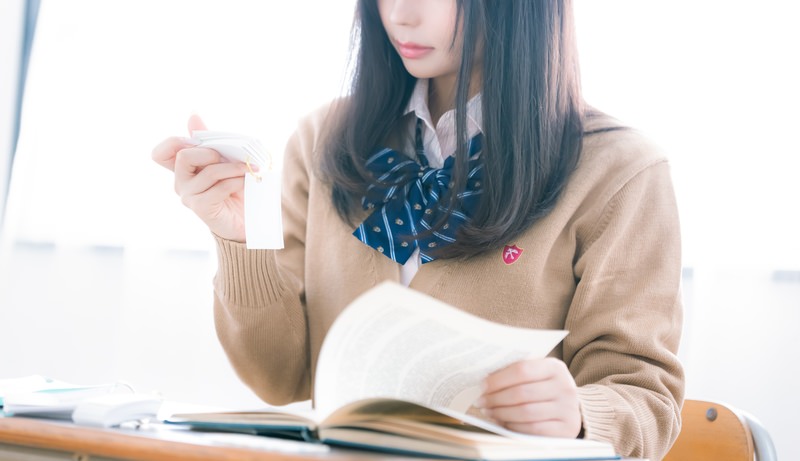









コメント