
中学生になると、勉強に対するモチベーションが急に下がったと感じる保護者の方は多いのではないでしょうか。
「前はあんなに頑張っていたのに…」「何を言ってもやる気がなさそう…」と不安になることもあるかもしれません。
実は、この時期の子どもたちは、心も体も大きく成長する中で、モチベーションが揺れやすい時期です。
今回は、保護者の皆さまができる「モチベーション低下を防ぐ5つのポイント」をご紹介します。
小さな「できた!」を積み重ねる

子どもが勉強に対して前向きになるためには、「自分でもやればできる」という実感が欠かせません。
そのために効果的なのが、小さな成功体験を積み重ねることです。
たとえば、
- 苦手な教科でも「1問だけ解けた」「昨日より解くスピードが上がった」
- 「今日も机に向かって10分勉強できた」
- 「漢字を5個だけ覚えられた」
といった、ほんの小さな達成でも構いません。
それを保護者の方が見つけてあげて、
- 「ちゃんとやってるね、すごいじゃん」
- 「昨日より進んでるね」
- 「5分でも始められたの、えらいね」
と、具体的な行動を認めてあげることがポイントです。
テストの点数や結果だけを褒めるのではなく、「過程」や「努力」に注目することで、子どもは“やれば認めてもらえる”という気持ちを持ち、少しずつ前向きに取り組むようになります。
また、子ども自身が「できたことを記録する」習慣もおすすめです。
- カレンダーに「今日やったこと」を一言だけ書く
- スタンプやシールで可視化する
など、目に見える形で成果を残すことで、自信につながります。
最初はほんの小さな一歩で構いません。
「できた!」の積み重ねが、やがて大きな「やる気」へとつながっていきます。
「勉強=将来の自分に役立つ」ことを伝える

中学生のお子さんからよく聞かれるのが、「こんなの勉強して将来何の役に立つの?」という疑問です。
これは決して否定すべきことではなく、思春期の自然な自己成長の一環です。
だからこそ、保護者の皆さまができる大切な働きかけのひとつが、「勉強が将来とつながっていること」を具体的に伝えることです。
子どもに響く“未来のイメージ”を見せる
「将来〇〇になりたい」という夢がある子には、その夢と今の勉強がどうつながっているかを具体的に示しましょう。
例:
- 「ゲームクリエイターになりたいなら、数学や英語がすごく大事なんだよ」
- 「動物のお医者さんになりたいなら、理科の知識が役立つよ」
まだ夢がはっきりしていない場合は、
- 「選べる仕事の幅を広げるために、基礎的な勉強が必要なんだよ」
- 「勉強しておくと、大人になったときに“やっておいてよかった”と思えるよ」
というように、可能性を広げる選択肢の一つとして伝えることが効果的です。
保護者自身の経験も「教材」になる
お父さん・お母さんの学生時代や社会人としての経験は、子どもにとって貴重な学びになります。
たとえば、
- 「あのとき、もう少し英語をやっておけばって今でも思うよ」
- 「お母さんは理科が好きで、それが今の仕事にもつながってるよ」
というように、“大人のリアルな声”として話すと説得力が増します。
正解を押しつけるのではなく、体験として語ることで、自然に子どもに届く言葉になります。
社会と学びの“つながり”を見せる
日常生活の中にも、勉強が活きている場面はたくさんあります。
- 買い物での割引計算 → 算数・数学
- 料理のレシピ → 理科(化学変化や温度管理)
- ニュースで見聞きする社会問題 → 社会・国語
こうした身近な話題から、「あっ、これ勉強とつながってるんだ」と気づかせてあげることが、勉強=現実に役立つものという意識を育てます。
将来に不安を感じたり、今の努力が意味を持たないと感じてしまったりする中学生にとって、勉強の“意味”を見出すことがやる気のきっかけになります。
焦らず、日常会話の中で少しずつ伝えていくことが大切です。
家庭の中に「安心して頑張れる空気」をつくる
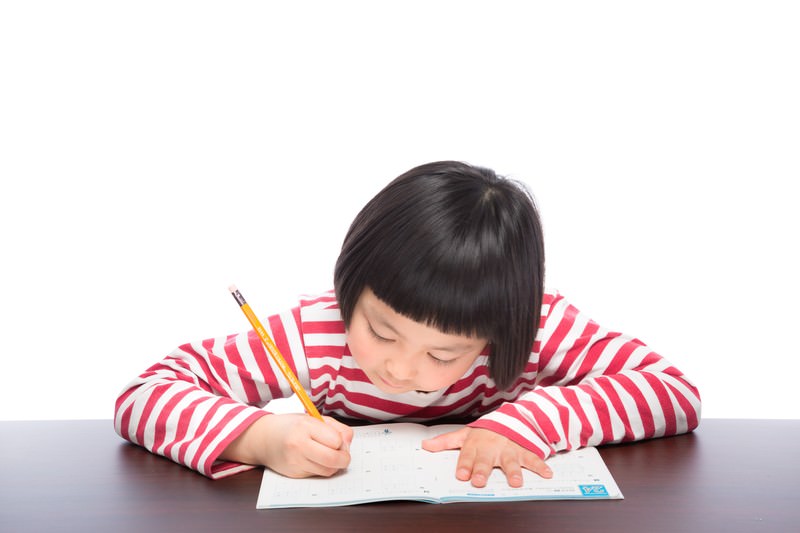
子どもが勉強に前向きになるためには、知識だけでなく心の土台が整っていることが大切です。
そのためには、家庭が「頑張ることを応援してもらえる」「失敗しても大丈夫」と感じられる、安心できる場所であることが大きな力になります。
「結果」より「努力」や「姿勢」に目を向ける
たとえばテストの点数が振るわなかったとき、つい「どうしてこんな点数なの!?」と叱ってしまいがちです。
でも子どもは、「頑張ったのに怒られた」という思いから、自信ややる気を失ってしまうことも。
そんなときはまず、
- 「よく最後まで諦めずに受けたね」
- 「ちゃんと提出物も出してたし、頑張ってたの見てたよ」
といったように、行動や努力の部分を肯定してあげる声かけが大切です。
結果を見て評価するのではなく、過程に寄り添うことで、安心して挑戦できる空気が生まれます。
子どもが「弱音を吐ける」「相談できる」雰囲気を意識する
思春期の子どもは、感情の起伏が激しく、悩みや不安をうまく言葉にできないこともあります。
「最近勉強してないな」と感じても、すぐに叱るのではなく、子どもの気持ちの背景を想像する姿勢が大切です。
声かけの例:
- 「疲れてるみたいだね。何かあった?」
- 「もし困ってることがあれば、いつでも話してね」
- 「気分が乗らない日もあるよね。無理しすぎなくて大丈夫だよ」
このように、子どもが“話してもいいんだ”と思える関係づくりが、長期的には勉強への前向きさを育てていきます。
“成功体験”よりも、“安心して失敗できる体験”を大切に
大人でも、ミスを厳しく責められる環境では新しいことに挑戦しづらくなります。
それは子どもも同じです。
たとえば、
- 「間違えたっていいよ、それも学びだね」
- 「うまくいかなかった理由を一緒に考えてみよう」
といった、失敗を受け入れる声かけが、子どもの「次は頑張ろう」という気持ちを支えます。
子ども自身を信じる姿勢が、何よりの応援になる
子どもは、大人が思う以上に親の言葉や表情を敏感に感じ取ります。
「この子はきっと伸びる」と信じる気持ちを持ち、
- 「あなたならできるよ」
- 「お母さん(お父さん)は応援してるよ」
という肯定的な言葉を、折に触れて伝えてあげてください。
そうした信頼が、子どもにとって「頑張ってみようかな」と思える、心の支えになります。
子どもが安心して勉強に取り組める環境づくりは、一朝一夕ではできません。
でも、「叱る」よりも「認める」「寄り添う」時間が少しでも増えれば、子どもは確実に変わっていきます。
家庭は、子どもにとって“最後のよりどころ”であり、最大の味方です。
スケジュールを一緒に立てる

中学生が勉強に対して「何からやればいいのか分からない」「時間の使い方が難しい」と感じることは少なくありません。
こうした見通しの立たなさや不安感が、やる気の低下につながっていることもあります。
そこで保護者の方が一緒に学習スケジュールを立てるサポートをすることで、子どもは「できそう!」という感覚を持ちやすくなります。
ポイント1:細かくしすぎず、「まずは一週間単位」で考える
あまりにも細かい計画を立てようとすると、子どもが窮屈に感じてしまい、逆にやる気をなくしてしまうことがあります。
最初は、
- 「1週間のうち、何日くらい勉強したい?」
- 「土曜日は部活が休みだから、少し多めにやってみる?」
といったざっくりとしたスケジュールづくりから始めるのがコツです。
紙のカレンダーやスケジュール帳、ホワイトボードなどを使って「見える化」すると、達成感も生まれやすくなります。
ポイント2:「短時間・具体的な目標」にする
中学生の集中力は大人ほど長く続きません。
そのため、「1日3時間勉強しよう」などの大きすぎる目標は避けて、“15分だけ”や“1ページだけ”といった短時間の目標を設定することがポイントです。
例:
- 「今日は理科の教科書を3ページ読む」
- 「漢字を5個だけ練習する」
- 「ワークの1問だけでもやってみよう」
こうしたハードルの低いスタートを設定することで、「やればできた」という成功体験につながります。
ポイント3:子ども自身に“決定権”を持たせる
スケジュールを親が一方的に決めてしまうと、子どもは「やらされている感」を強く持ってしまいます。
そうならないためにも、子ども自身に選ばせる関わり方が効果的です。
たとえば、
- 「国語と英語、どっちからやってみる?」
- 「夕方と夜、どっちが集中できそう?」
- 「明日はどれをやる?」
など、小さな選択肢を提示しながら、自分で決める感覚を持たせましょう。
こうした体験が「勉強=自分のもの」と思える自立心につながります。
ポイント4:「できた日」はしっかり認め、続ける力に
計画通りにいった日は、しっかりと褒めたり、達成マークをつけたりして**“見える達成感”を演出**しましょう。
おすすめは、
- カレンダーにチェックマークを入れる
- スタンプやシールを貼る
- 「よくやったね」と声をかける
こうした小さな積み重ねが「続ける力」を育てます。
スケジュール作り=“親子の会話のきっかけ”にもなる
スケジュールを一緒に考える時間は、単に勉強の計画を立てるだけでなく、
- 「最近疲れてない?」
- 「学校の授業どう?」
- 「テストに向けて、今何が不安?」
など、日々の様子を知る良いチャンスにもなります。
子どもは、「先の見通し」が立つと行動に移しやすくなります。
親子で一緒にスケジュールを立てることで、勉強に対する“心理的ハードル”を下げ、無理なく前向きに取り組めるようになります。
「がんばること」ではなく「続けやすくすること」を意識して、ぜひ親子で楽しく取り組んでみてください。
学校や塾以外の「第三者」の存在を活用する

勉強のモチベーションが下がっているとき、親や先生以外の人のひとことが、思いがけず子どもに響くことがあります。
子どもにとって、家庭や学校とは少し違う立場の人――たとえば信頼できる年上の人や、少し距離のある大人が、実は大きな支えになることがあります。
これは、家庭でも学校でもない“第三の安心できる居場所”のような役割を果たしてくれるからです。
こんな「第三者」が、子どもの支えになります
- 部活や習い事の先生
(※勉強と関係ない分、気軽に話せる場合も) - 兄姉や親戚の大学生・社会人
- 家庭教師や地域の学習ボランティア
- 通っている塾の講師(特に年齢の近い講師)
- SNSや動画で出会う“少し上の世代”のロールモデル
たとえば、塾の講師が何気なく話した「○○くんもこの時期は伸び悩んでたけど、乗り越えたよ」という言葉が、親の何倍も心に残ることがあります。
子どもが“受け入れやすい距離感”が大事
親からの言葉はどうしても「指導」や「期待」の色が強くなりがちですが、第三者からの声は、
- プレッシャーを感じにくい
- 客観的に聞きやすい
- 自分で「納得する」きっかけになりやすい
というメリットがあります。
特に中学生は、「親以外の大人の目」を気にし始める時期でもあります。
第三者の励ましは、そうした心理にも自然に寄り添いやすいのです。
保護者の関わり方の工夫
保護者の方にできることは、「第三者の存在をつくってあげる」ことと、「その人とつながる機会を整える」ことです。
たとえば:
- 信頼できる塾の先生や家庭教師に、「最近少し元気がないようなので、気にかけてもらえますか?」とさりげなく相談する
- 大学生の知り合いに、「受験のときどんなふうに勉強してた?」と子どもに話を聞かせてもらう
- 子どもが動画やSNSで尊敬する人を見つけたら、「その人が中学生のときどう過ごしてたか調べてみたら?」と促してみる
子どもが“素直に聞ける人”や“目標にできる人”と出会える機会は、勉強に対する価値観を大きく変えるきっかけにもなります。
無理に探す必要はありませんが、“そういう選択肢もある”という意識を
「親が何を言っても響かない…」と感じるときほど、第三者の力は有効です。
もちろん無理に誰かを探す必要はありませんが、「この子には、家庭・学校以外のつながりもある」と思えるだけで、保護者の心も少し軽くなるはずです。
勉強のモチベーションは、必ずしも親の言葉や塾の指導だけでは上がらないものです。
子どもが自分で「変わりたい」と思えるきっかけを与えてくれる存在が、身近に一人でもいることは、何よりの心の支えになります。
ぜひ、子どもにとっての“第三の応援者”がどこかにいないか、意識してみてください。
最後に

モチベーションの低下は、どんなお子さんにも起こるものです。大切なのは、「やる気がない=ダメなこと」と決めつけず、親子で一緒に乗り越えていく姿勢です。
子どもにとって一番の応援団は、やはり保護者の皆さま。少しの工夫と温かなまなざしで、お子さんの「やってみよう」を引き出していきましょう。



コメント